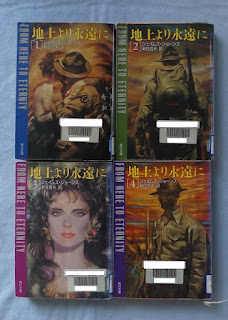今年もあとわずか。いろいろあったけれど、バルザックの「幻滅」、メルヴィルの「白鯨」、そしてプーシキンを読んだのは、私にとっては画期的なことだった。
バルザックは大学時代にフランス語で中編を読んだだけ。メルヴィルは同じころ、中編「バートルビー」を翻訳で読んだだけ。プーシキンは読もうとすら思わなかった。
それが、フランス映画「幻滅」を見てバルザックの長大な原作を読み、「ザ・ホエール」を見て「白鯨」を読み、そして今、プーシキンを読もうとしている。
正直、バルザックの長編、メルヴィルの「白鯨」、プーシキンは一生読まないだろうと思っていた。それが今年見た映画がきっかけで読み、年末になってあることからプーシキンに興味を持って図書館に行き、プーシキン全集を借りてきた。
借りてきたのは有名な「エヴゲニー・オネーギン」が入った巻。それ以外に「モーツアルトとサリエリ」という短い劇が入った巻があり、2巻借りるのは重いので、こちらは図書館で読んだが、とても面白かった。「アマデウス」よりいいんじゃないの?と思い、その場で2回読んでしまったほど。
というわけで、プーシキン全集の1冊と、ついでに借りた「森下洋子自伝」。森下洋子のバレエは「くるみ割り人形」と「眠れる森の美女」を見てるけど、80年代末で、もうだいぶ前だなあ。カードは図書館で配っていたもの。
このほか、遠方の図書館にある「プーシキンとロシア・オペラ」という本を予約して、それを取りに行ったついでに、たまたま目にしたマツモトキヨシ伝と、「野性の棕櫚」の入ったフォークナー全集を借りる。
マツモトキヨシ伝は松戸の話なので、郷土資料となり、千葉県立図書館では2冊が貸出不可、1冊が貸出可で、これを棚に見つけて借りた。マツキヨ創業者、元松戸市長の松本清の作ったすぐやる課はすごく有名で、リアルタイムで知っていた。
で、松戸市立図書館にはあるのかな、と思って調べたら、こちらは2冊あって2冊とも貸出不可。出た当初は借りる人多かっただろうけど、その後は借りる人がいなくてこれだけになってしまったのかな。貸出不可しかないのはきびしい。
そしてさらに調べたら、「マツモトキヨシ80年史」という本が市立図書館にあり、貸出可能だったので予約中です。
これはマツモトキヨシホールディングスが出した非売品なので、松戸市に寄贈したものでしょう。とはいえ、通販で売っているところがある。写真は通販サイトのものです。
「プーシキンとロシア・オペラ」は、これまでプーシキンに興味がなく、ロシア・オペラも興味なかったのだけど、プーシキン全集を見ていたら「金鶏」があり、リムスキー・コルサコフのオペラ「金鶏」はボリショイ劇場の日本公演を見たことがあったので、興味を持った。
ボリショイの「金鶏」を見たのは1989年。このときの演目は「ボリス・ゴドノフ」「金鶏」「エヴゲニー・オネーギン」の3作で(いずれもプーシキン原作)、有名で人気のある「ゴドノフ」と「オネーギン」にはさまれた地味な「金鶏」だけをなぜ見に行ったのか、さだかではない。「金鶏」はソ連時代にはあまり上演されず、ペレストロイカになって再評価された、というので見に行ったのかもしれない。
「金鶏」は3公演のうち、2回がベテランのソプラノ、1回が若手のほぼ無名のソプラノで、人と違ったことをする私はあえてこの無名のソプラノの回のチケットを買った(よい席がとれました)。
そして見に行って驚いた。この若手のソプラノ、歌もうまいし美人でスタイルもよく、へそ出しルックの衣装で歌い踊る。うおお、堅物ソ連のオペラとは思えん、これがペレストロイカか、とびっくりし、オペラもファンタジーで楽しく、とーっても満足。その後、この回を見逃したオペラファンのおじさんたちが悔しがったというおまけもついたのだった。
プーシキンといえばこの思い出しかなかったのだけど、これからいろいろ読みます。
そして、フォークナーの「野性の棕櫚」。この全集では「野性」ですが、ほかでは「野生」となってます。
「PERFECT DAYS」の中で役所広司が読んでいる3冊の本の1冊で、映画では大久保康雄訳の新潮文庫でしたが、すでに絶版。それどころか図書館にもほとんどない。私がカード持ってる図書館はどこもなかった。
戦後の時代、数多くの英米文学を翻訳した大久保康雄、実際は大久保工場と呼ばれる翻訳家集団で、大久保本人の訳だけでなく、大久保のもとに集まった優れた翻訳家たちが大久保の名前で訳していたようなのですが、その多くは新潮文庫に入っていたのです。ところが新潮文庫が新訳を次々と出し、大久保訳は絶版になり、図書館も新訳を入れるから大久保訳は一部を除いてどんどん廃棄になっているような気がします。
古い名訳は今の人には読めない、というのは事実なのですが、それでも歴史の遺産であるこうした名訳が国会図書館のようなところでしか読めなくなるのは悲しい。
実は映画に合わせるように、中公文庫が11月に加島祥造の古い訳を復刊して、そちらはあちこちの図書館に入ってますが、貸出中が多い。まあみんなこれ読むよね。
加島はフォークナーをほかにも訳していて、私が若い頃に読んだ3大代表作「響きと怒り」「八月の光」「アブサロム、アブサロム」のどれかが彼の訳だったはず。
とにかく新潮文庫の大久保訳はほとんどないわ、中公のは貸出中だわ、で、借りてきたのがフォークナー全集の「野性の棕櫚」。こちらはアメリカ文学者の訳ですが、やっぱり大久保訳が見たい、という思いもあり、いろいろ調べたところ、河出書房の古い全集に入っているのを発見。これが県立図書館の遠方の館にあるので予約。中公文庫も一応、予約待ちにしてますが、これで3つの翻訳を比べられるなあ、って、いったい何をしてるんだ、自分。
昔はフォークナーの翻訳って、普通に本屋さんにいっぱいあって、人気作家だったのに、いつのまにか翻訳が手に入らなくなってるな、ということはだいぶ前から感じていました。でも代表作は新訳で出たりしてるので、人気がないわけではないのかな、と思っていたけれど、今回、「野生の棕櫚」の件で、やっぱりフォークナーは最近人気ないんだ、人気あったのは大橋健三郎が東大教授だったから?などと考えてしまったのです。
あの頃はアメリカ文学研究といったら、フォークナーだったんですよ。
映画に出てきたパトリシア・ハイスミスの「11の物語」も貸出中で、こちらも予約待ちです。